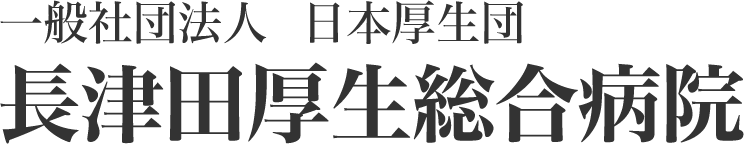長津田厚生総合病院の閉院延期ついて
一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院は、2024年(令和6年)3月31日の閉院予定を延期し、2024年(令和6年)4月30日をもちまして閉院いたします。
患者様やご利用者様、関係者や地域の皆様には、多大なるご迷惑とご不便をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。
※長津田厚生総合病院としての保険診療は一切行いません。
→長津田厚生総合病院 閉院のお知らせ(PDF/2023年12月21日)
4月1日以降の診療に関して
2024年(令和6年)4月1日より、現在の敷地内で新たな診療所「長津田厚生クリニック」が、保険医療機関として、内科外来・眼科外来・泌尿器科外来・訪問診療の一部診療を開始いたします。(入院診療は行いません。)
| 医療機関名 | 長津田厚生クリニック |
|---|---|
| 診療科 | 循環器内科・消化器内科・腎臓内科・呼吸器内科・糖尿病内分泌内科・眼科・泌尿器科 |
| 受付時間 | 月~金/午前8:30~11:00、午後12:00~16:00 土/午前8:30~11:00、午後 休診 日・祝日/休診 |
| 診療開始時間 | 午前9:00~、午後14:00~ |
| 電話番号 | 045-981-1203 |
※各科の診療時間等の詳細につきましては下記外来診療担当一覧表をご覧ください。
※お支払いは現金のみになります(クレジットカード・電子マネーはご利用できません)。